- LP
- Recommended =
- New Release
Enno Velthuys
Music From the Other Side of the Fence
Stroom
- Cat No.: STRLP-076
- 2026-02-28
〈Light In The Attic〉のコンピ『(The Microcosm) Visionary Music Of Continental Europe, 1970-1986』にセレクトされ、これまで母国オランダの〈Dead Mind〉が主に発掘にいそしんできた孤高のシンセシストEnno Velthuysの1975年〜1990年の音源をまとめた未発表のアーカイヴ作品集をベルギーの〈Stroom〉がリリース。孤独のシンセブルース。音楽は彼の言葉でした。
Track List


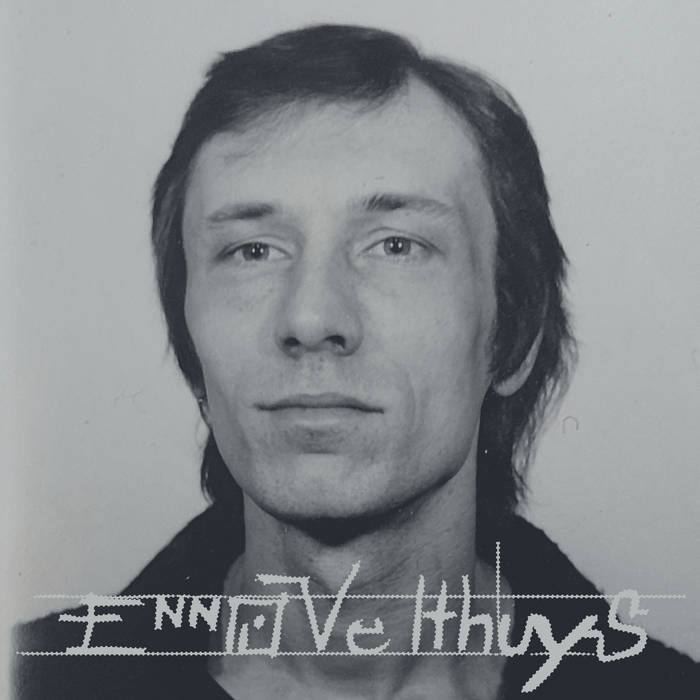
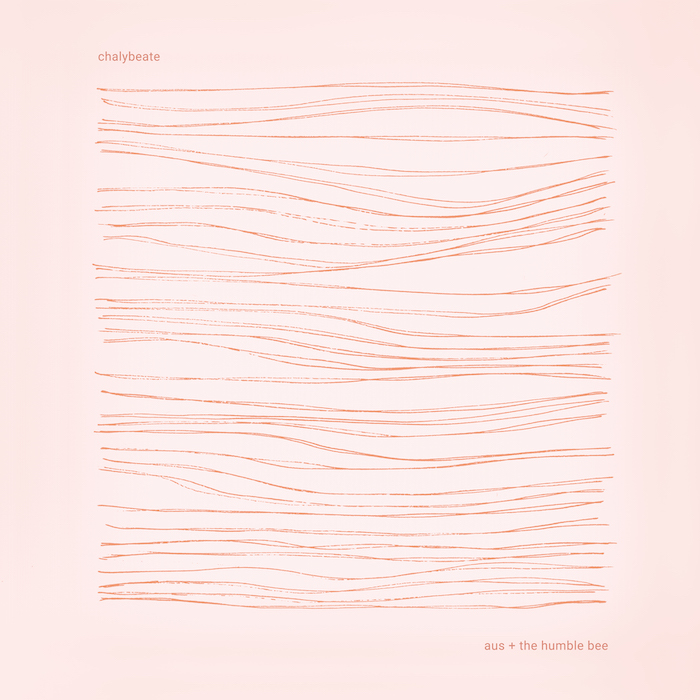


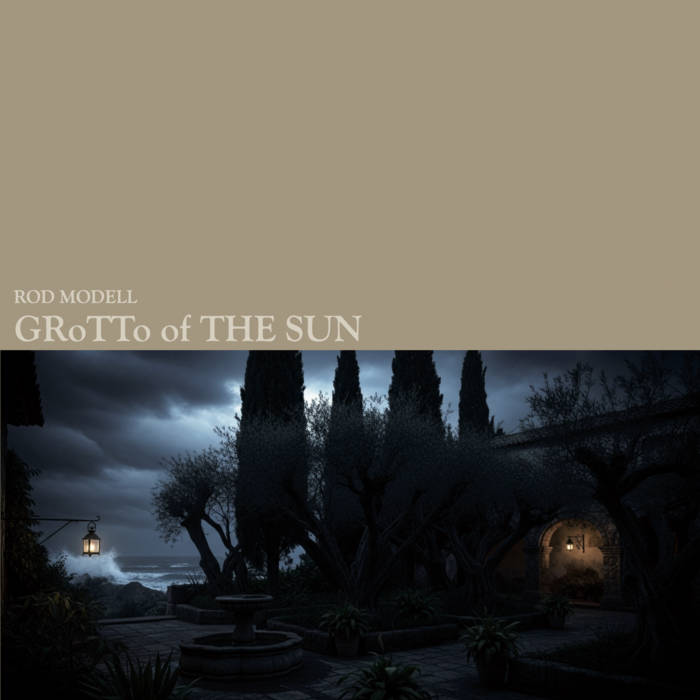
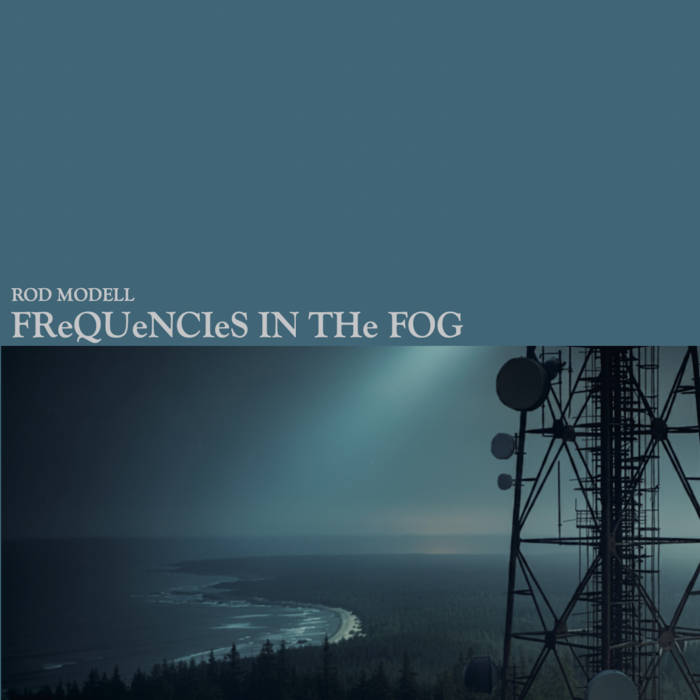
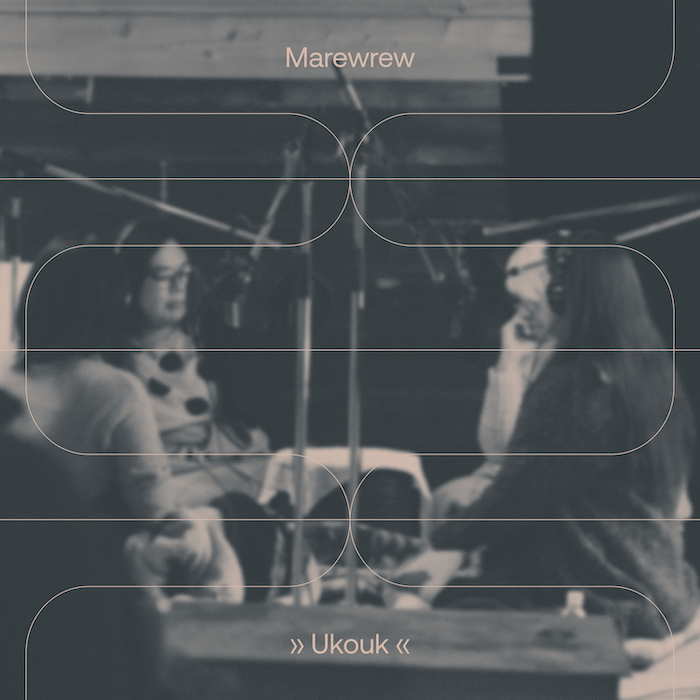




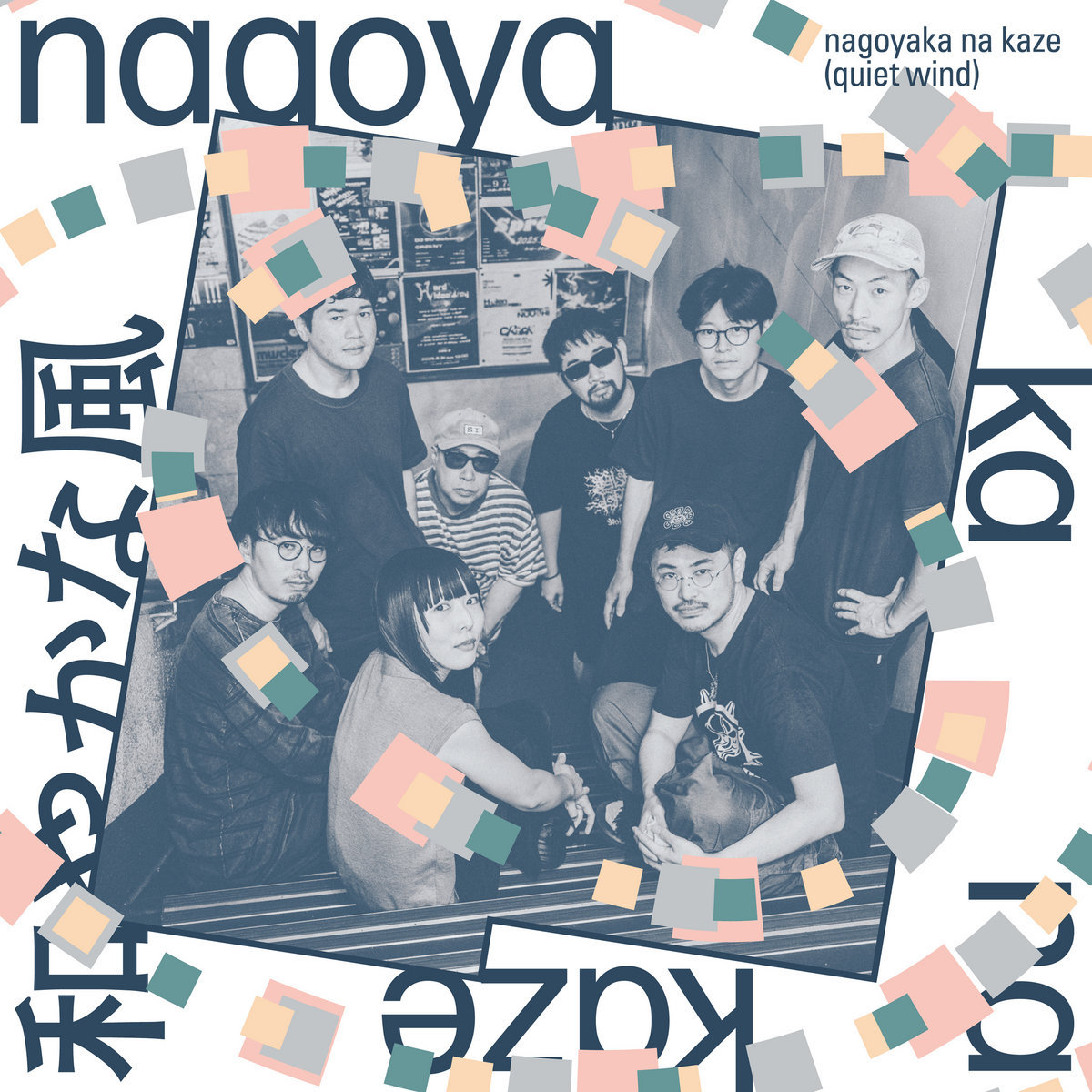


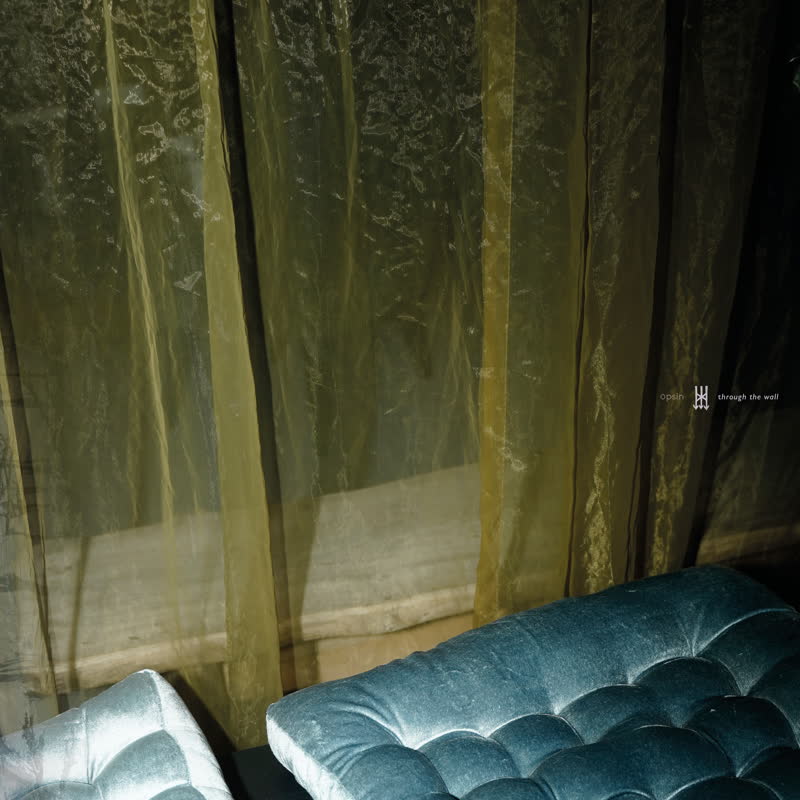


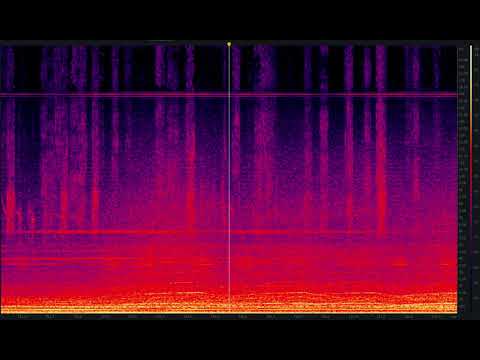

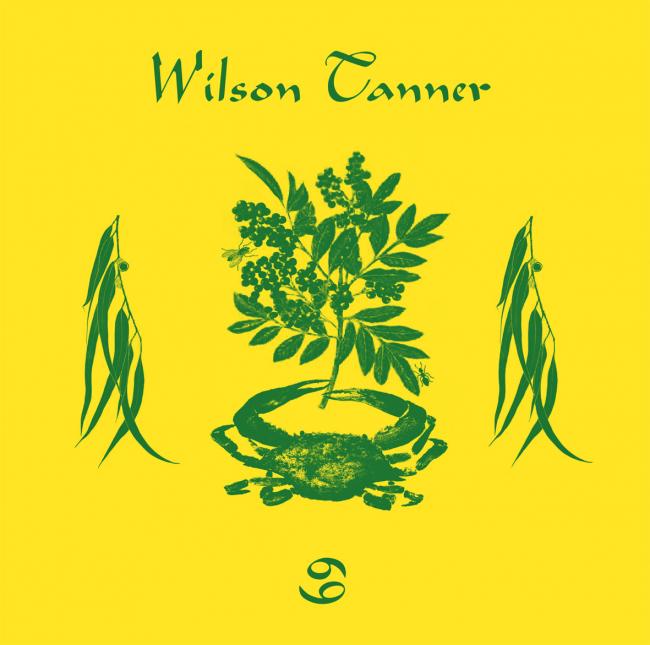
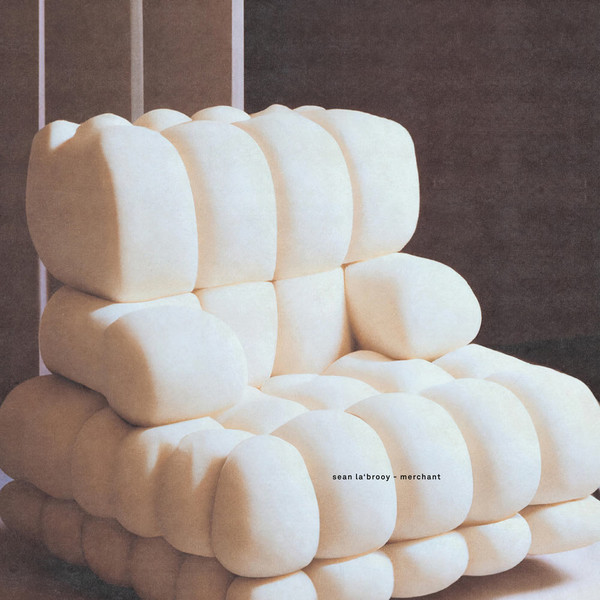


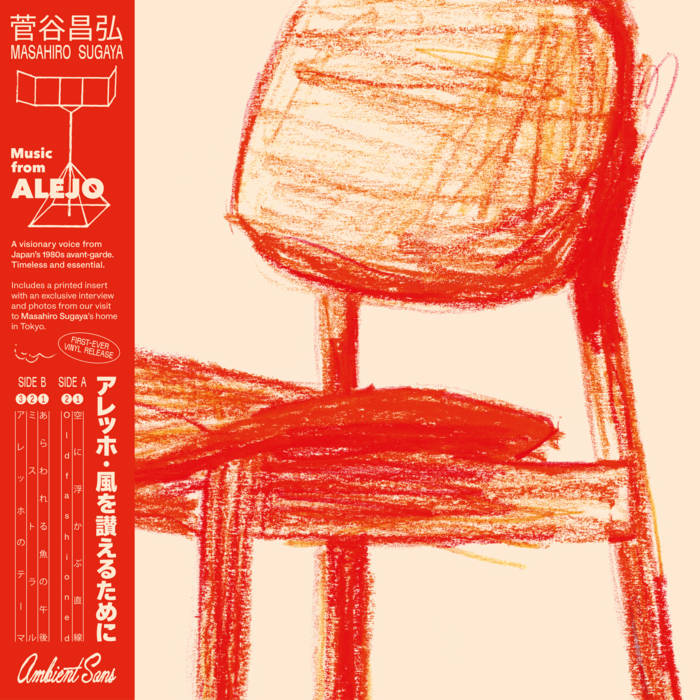
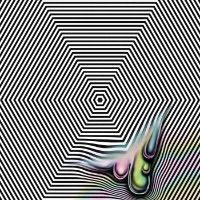
夢想家のプライベート・アトリエを覗き見るような極めて私的な作品群が、オブスキュアな発掘で名高い〈Stroom〉の仕事によってお目見え。50年代のインスト・ギターや60年代ビート、70年代初期アンビエント、ウエスタン風の旋律、エリック・サティ的要素までを溶け合わせた、夢見心地でありどこか不穏で疎外感を漂わせる独自のサウンド。セックス、ドラッグ、ロックンロールを経て、焦点を失い、孤立した暮らしを送った孤独に愛された人物だったようです。コンパイルは自身も〈Stroom〉などから作品を発表している音楽家Hessel Veldmanが担当。エンノはほとんど曲名を考えることがなかったようで、本作では多くの曲名をHesselが考案したということです。手放しで推薦してしまいたくなる魅力があります。 (足立)